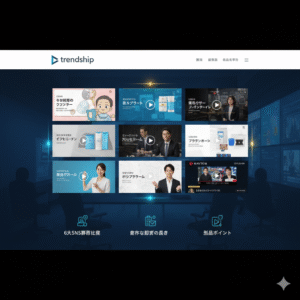「自社の魅力を伝えるPR動画を作りたいけど、何から手をつければいいんだろう?」 「効果的なPR動画の作り方が分からず、なかなか一歩を踏み出せない…」
企業のマーケティングや広報を担当する中で、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
スマートフォンやSNSの普及により、誰もが日常的に動画に触れる時代になりました。テキストや画像だけでは伝えきれない情報や世界観を、映像と音で直感的に伝えられるPR動画は、今や企業や自治体にとって欠かせないマーケティングツールです。
しかし、ただやみくもに動画を制作しても、期待する効果は得られません。数多ある動画コンテンツの中で視聴者の心をつかみ、行動を促すためには、戦略的な企画と制作のコツを押さえることが不可欠です。
そこでこの記事では、Webメディア「trendship」の編集部が、効果的なPR動画の作り方を7つのステップで徹底解説します。企画の立て方から撮影・編集の具体的なコツ、参考にしたい成功事例、さらには自社制作と外注の判断基準まで、PR動画制作に関するあらゆる疑問を解決します。
この記事を最後まで読めば、あなたの会社やサービス、地域の魅力を最大限に引き出し、視聴者の心に響くPR動画を制作するための具体的なノウハウが身につくはずです。ぜひ、次なる一手のためのヒントを見つけてください。
そもそもPR動画とは?注目される理由とメリットを再確認
まずは基本に立ち返り、PR動画がなぜこれほどまでに重要視されているのか、その定義とメリットを改めて確認しておきましょう。
PR動画の定義と目的
PR動画とは、企業や地方自治体が、自社の商品・サービス、ブランドイメージ、あるいは地域の魅力などを広く伝えるために制作する動画コンテンツのことです。
その目的は多岐にわたりますが、主に以下のようなものが挙げられます。
- 商品・サービスの認知度向上、販売促進
- 企業のブランディング、イメージアップ
- 採用活動におけるミスマッチの防止、応募者数の増加
- 地方自治体の観光誘致、移住促進
テレビCMとは異なり、YouTubeやSNSなど、Webプラットフォームを中心に配信されることが多く、ターゲットを絞った的確なアプローチが可能な点も大きな特徴です。
なぜ今、PR動画が重要なのか?
情報が溢れかえる現代において、PR動画の重要性はますます高まっています。その背景には、以下のような理由があります。
- 短時間で圧倒的な情報量を伝えられる 動く映像と音を組み合わせた動画は、テキストや静止画に比べて格段に多くの情報を伝えることができます。ある調査では、1分間の動画が伝える情報量は、Webページ約3,600ページ分に相当するとも言われています。
- スマートフォンとSNSの普及 誰もがスマートフォンを持ち、日常的にSNSを利用するようになったことで、動画コンテンツは私たちの生活に深く浸透しました。ユーザーが自ら面白いと感じた動画をシェアすることで、爆発的な拡散が生まれる可能性も秘めています。
- 記憶に残りやすい 視覚と聴覚の両方に訴えかける動画は、視聴者の感情を揺さぶり、強い印象を残します。アメリカ国立訓練研究所が提唱する「ラーニングピラミッド」においても、視聴覚を組み合わせた学習は、テキストを読むだけの場合よりも記憶の定着率が高いとされています。
PR動画を制作する具体的なメリット
これらの背景を踏まえると、PR動画を制作することには、以下のような具体的なメリットがあると言えるでしょう。
- 複雑な情報も直感的に伝えられる サービスの利用手順や商品の複雑な機能など、文章では説明しにくい内容も、動画なら実際の動きを見せることで直感的に理解を促せます。
- SNSでの拡散による認知拡大が期待できる 共感を呼んだり、インパクトがあったりする動画は、SNSでシェアされやすく、広告費をかけずとも幅広い層にリーチできる可能性があります。
- 企業のブランドイメージや世界観を伝えやすい 映像のトーン、BGM、ナレーションなどを通して、企業が大切にしている理念や独自のカルチャーといった、言語化しにくい「空気感」を伝えることができます。
- 時間や場所を選ばずにアプローチできる Web上に公開された動画は24時間365日、世界中のどこからでもアクセス可能です。これまでアプローチできなかった潜在顧客層にも、魅力を届けるチャンスが広がります。
【完全ガイド】効果的なPR動画の作り方 7ステップ
それでは、いよいよ具体的なPR動画の作り方を7つのステップに沿って解説していきます。この流れを意識することで、制作プロセスがスムーズに進むだけでなく、動画のクオリティも格段に向上するはずです。
ステップ1:企画の核を固める「目的」と「ターゲット」の明確化
PR動画制作において、最も重要といっても過言ではないのが、この最初の企画ステップです。ここで方向性を誤ると、どんなにクオリティの高い映像を作っても、望む成果にはつながりません。
まずは、「何のために(目的)」「誰に(ターゲット)」この動画を届けたいのかを徹底的に考え、明確な言葉で定義しましょう。
- 目的の例
- 新商品の認知度を上げ、発売初月の売上目標を達成する
- 企業のブランディング動画で共感を醸成し、採用サイトへのアクセス数を20%増やす
- サービスの魅力を伝え、無料トライアルへの申し込みを月50件獲得する
- ターゲット設定
- 「20代女性」といった漠然とした設定ではなく、「都内在住で、オーガニックコスメに関心が高い28歳のOL。情報収集は主にInstagramを利用している」というように、具体的な人物像(ペルソナ)まで掘り下げることが重要です。
ターゲットが明確になれば、その人が普段どんなSNSを使い、どんなコンテンツに興味を持つのかが見えてくるため、動画のテイストや配信媒体の選定もしやすくなります。
この段階で、「5W1H」のフレームワークを使って情報を整理するのも非常に有効です。
- Why(なぜ):なぜこの動画を作るのか?(目的)
- Who(誰に):誰に見てほしいのか?(ターゲット)
- What(何を):何を一番伝えたいのか?(メッセージ)
- When(いつ):いつ配信するのか?(タイミング)
- Where(どこで):どの媒体で配信するのか?(プラットフォーム)
- How(どのように):どのように見せるのか?(表現方法)
ステップ2:心に響く「メッセージ」を一つに絞り込む
自社の商品やサービスには、伝えたい魅力がたくさんあることでしょう。しかし、PR動画で成果を出すためには、その中から最も伝えたいメッセージを「一つ」に絞り込む勇気が必要です。
短い動画の中に多くの情報を詰め込みすぎると、結局何が言いたいのかがぼやけてしまい、視聴者の記憶に何も残りません。「安さ」も「品質」も「デザイン性」も、となるとメッセージが散漫になります。
「この動画を見終わった後に、視聴者にどんな言葉を覚えておいてほしいか?」を自問自答し、シンプルで強力なコアメッセージを決めましょう。
ステップ3:視聴者を惹きつける「構成・シナリオ」の作成
目的、ターゲット、メッセージが固まったら、それをどのように映像で表現していくか、具体的な構成とシナリオを作成します。
- ストーリーテリングを意識する 単なる情報提供ではなく、視聴者が感情移入できるようなストーリーを描くことが重要です。「起承転結」のような物語のフレームワークを取り入れ、視聴者の心を動かす流れを作りましょう。
- 冒頭の5秒で心を掴む 多くの視聴者は、動画の冒頭数秒で「続きを見るか否か」を判断します。インパクトのある映像や、好奇心を刺激する問いかけなど、視聴者が思わず引き込まれるような「フック」を用意することが成功の鍵です。
- 視聴者に「自分ごと化」させる 視聴者が「これは自分のための動画だ」と感じられるような仕掛けが効果的です。例えば、ターゲットが抱えるであろう悩みを冒頭で提示し、その解決策として商品やサービスを紹介する構成などが考えられます。
この段階で、具体的なセリフやナレーション、シーンの展開を書き出した「シナリオ(台本)」と、それをイラストで視覚化した「絵コンテ」を作成します。絵コンテは、撮影や編集の設計図となる非常に重要なものです。関係者全員でイメージを共有し、この時点で内容をしっかりと固めておきましょう。
ステップ4:動画のクオリティを左右する「撮影準備」
シナリオと絵コンテが完成したら、いよいよ撮影の準備に入ります。準備の質が、動画全体のクオリティを大きく左右します。
- ロケーション・ハンティング(ロケハン):動画の世界観に合った撮影場所を探し、事前に下見を行います。
- 機材の選定:カメラやマイク、照明など、どのような映像を撮りたいかに合わせて必要な機材を準備します。
- キャスティング:動画に出演するキャストを選定します。社員に出演してもらうのか、プロの役者に依頼するのか、目的や予算に応じて検討します。
ちなみに、「PR動画はスマホでも撮影できる?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。結論から言うと、撮影は可能です。現代のスマートフォンはカメラ性能が非常に高く、SNS用の短い動画や、あえて手作り感を演出したい場合には有効な選択肢です。
しかし、企業のブランドイメージを左右するような重要な動画や、高いクオリティが求められる場合には、やはりプロ用の機材と技術を持った専門家に依頼することをおすすめします。
ステップ5:メッセージを映像に落とし込む「撮影」
入念な準備を経て、撮影本番に臨みます。当日は、絵コンテに沿ってスムーズに撮影を進められるよう、段取り良く進めていきましょう。
撮影で特に意識したいのは、動画を通して「信頼感」や「清潔感」が伝わるような映像を撮ることです。心理学の「メラビアンの法則」によれば、人がコミュニケーションで受け取る情報のうち、視覚情報(表情、しぐさなど)が55%、聴覚情報(声のトーン、話す速さなど)が38%を占めると言われています。
つまり、出演者が話す内容そのものよりも、その表情や話し方のほうが、視聴者に与える印象を大きく左右するのです。出演者には、リラックスして自然な笑顔で話してもらうよう心がけましょう。
また、撮影現場には必ずプロジェクトの最終判断ができる責任者が立ち会うことが重要です。後から「あのシーンが足りなかった」となっても、再撮影には多大なコストと時間がかかってしまいます。撮り漏れがないか、その場でしっかりと確認しましょう。
ステップ6:魅力を最大限に引き出す「編集」
撮影した映像素材を、より魅力的で伝わりやすい一本の動画に仕上げていくのが編集作業です。
- カット編集:不要な部分を削り、映像をつなぎ合わせます。視聴者が飽きないよう、テンポ感を意識することが非常に重要です。ターゲットが若年層なら速いテンポで、シニア層ならじっくり見せるなど、ターゲットに合わせた調整が求められます。
- テロップ(字幕):メッセージを補強し、音声が出せない環境でも内容が伝わるようにテロップを入れます。フォントやサイズ、色などを工夫し、視認性とデザイン性を両立させましょう。
- BGM・効果音:動画の世界観を演出し、視聴者の感情に訴えかける重要な要素です。選曲ひとつで動画の印象は大きく変わります。著作権フリーの音源サイトなどを活用しましょう。
- ナレーション:プロのナレーターに依頼することで、動画に安定感と説得力が生まれます。声のトーンや話すスピードも、動画のターゲットや目的に合わせて調整します。
- 色調・音声調整:映像全体の明るさや色味、音量を整えます。視聴者にとって見やすく、聞きやすい状態に調整するのは、編集の基本であり最も重要な作業の一つです。
ステップ7:作っただけで終わらない「活用・分析」
動画が完成したら、いよいよ公開です。しかし、PR動画は作って終わりではありません。設定した目的に対して、どれだけの効果があったのかを測定し、次につなげることが重要です。
- 配信プラットフォームの選定:YouTube、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、自社サイトなど、ターゲットユーザーが最も多く集まる場所を選んで動画を公開します。
- 効果測定と分析:視聴回数や視聴維持率、エンゲージメント率(いいね、コメント、シェア数)、ウェブサイトへの流入数などを分析します。どこで視聴者が離脱しているのか、どんな層に見られているのかを把握し、改善点を見つけましょう。
- 「届ける努力」を怠らない:素晴らしい動画を作っても、見てもらえなければ意味がありません。動画SEO(VSEO)を意識したタイトルや説明文を設定したり、SNS広告を活用したりと、ターゲットに動画を「届ける」ための工夫も必要不可欠です。
【目的別】参考にしたいPR動画の成功事例5選
ここでは、PR動画の作り方をより具体的にイメージできるよう、優れた成功事例を目的別にご紹介します。各動画がどのような工夫で視聴者の心を掴んでいるのか、そのポイントを分析してみましょう。
企業ブランディング事例:SEIKO「日頃目にすることがない部品が、世界の当たり前を支えている」
時計で有名なSEIKOの企業PR動画です。この動画では、特定の製品をアピールするのではなく、時計の精密部品を作る高い技術力が、実は社会の様々な「当たり前」を支えているというストーリーを描いています。視聴者は、自社の技術に対する誇りと社会への貢献姿勢を感じ取り、SEIKOというブランドへの信頼と好感を深めることになります。商品を直接的に宣伝しないことで、かえって企業の価値を高めることに成功した好例です。
商品・サービス紹介事例:西部ガス「ガス衣類乾燥機」
実演販売士を起用し、ガス衣類乾燥機の魅力を巧みな話術で紹介する動画です。主婦が抱える「洗濯物を干す手間の大変さ」という悩みに寄り添い、共感を誘うところから始まります。そして、天日干しとの比較を視覚的に見せたり、実際にお手入れの簡単さを実演したりすることで、商品のメリットを「自分ごと」としてリアルに感じさせます。視聴者の課題解決という視点で作られた、非常に説得力の高いPR動画です。
採用活動事例:株式会社YSK「SOMETHING NEW」
社員へのインタビューを中心に構成された採用PR動画です。実際に働く社員たちが、入社理由や仕事のやりがい、社内の雰囲気などを自らの言葉で語ることで、求職者は入社後の自分を具体的にイメージすることができます。作り込まれた言葉よりも、社員のリアルな声のほうが、企業のカルチャーや働きがいを何倍も雄弁に物語るということを教えてくれます。
観光・地域PR(話題性)事例:宮崎県小林市「ンダモシタン小林」
公開当時、大きな話題を呼んだ宮崎県小林市の移住促進PR動画です。一見すると、フランス人男性がおしゃれな雰囲気で街の魅力をフランス語で語っているように見えますが、実は全て小林市の方言「西諸弁(にしもろべん)」だった、という驚きのオチが待っています。この意外性がSNSで爆発的に拡散され、小林市の知名度を飛躍的に高めました。強いインパクトと話題性を狙った戦略的なPR動画の傑作です。
観光・地域PR(共感)事例:大村市移住・定住推進PR動画
長崎県大村市の移住促進PR動画です。思春期の娘が「大村市なんて大嫌い」と反抗的な態度で語り始めますが、その言葉とは裏腹に、描かれるのは心温まる地域の日常や人のつながりです。都会にはない「当たり前の幸せ」を逆説的に描くことで、視聴者の共感を呼び、地域の魅力を深く印象付けます。キャッチーなフレーズとストーリーテリングで、心に響くPRに成功しています。
PR動画制作、自社で行う?外注する?判断のポイント
PR動画の作り方が分かってくると、次に悩むのが「自社で作るべきか、プロに外注すべきか」という点でしょう。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の状況に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。
自社内製(インハウス)のメリット・デメリット
- メリット
- コストを抑えられる
- 社内での意思疎通が早く、スピーディーな修正対応が可能
- 商品やサービスへの理解が深く、メッセージを正確に反映させやすい
- デメリット
- 動画制作の専門知識やスキルを持つ人材が必要
- 専用の機材や編集ソフトなど、初期投資がかかる
- 客観的な視点が欠け、独りよがりな内容になるリスクがある
- 通常業務に加えて制作リソースを確保する必要がある
外注(制作会社・フリーランス)のメリット・デメリット
- メリット
- プロの技術による高品質な動画が期待できる
- 客観的な視点から、効果的な企画や演出の提案がもらえる
- 最新のトレンドを取り入れた動画を制作できる
- 自社のリソースを制作業務に割かずに済む
- デメリット
- 制作費用がかかる(費用相場は数十万〜数百万円と幅広い)
- 依頼先とのコミュニケーションに手間や時間がかかる場合がある
- 数多くの制作会社やクリエイターの中から、信頼できる依頼先を見つけるのが難しい
こんな場合は外注がおすすめ!判断基準をチェック
どちらを選ぶか迷った際は、以下の項目をチェックしてみてください。一つでも当てはまる場合は、プロへの外注を検討することをおすすめします。
- 企業のブランドイメージを左右するような、非常に重要な動画を制作したい
- 社内に動画制作の専門知識や経験を持つ人材がいない
- 撮影や編集に高い技術(CG、アニメーション、ドローン撮影など)が求められる
- 動画制作に割ける時間や人的リソースが十分にない
- 客観的な視点やプロならではのアイデア、提案が欲しい
失敗しない!PR動画の外注先選び3つのチェックポイント
外注を決めた場合に、次に重要になるのが「どこに依頼するか」です。数ある制作会社やフリーランスクリエイターの中から、自社に最適なパートナーを見つけるための3つのポイントをご紹介します。
Point 1:作りたい動画のテイストと「実績」が合っているか
まずは、依頼を検討している会社のウェブサイトなどで、過去の制作実績(ポートフォリオ)を必ず確認しましょう。その上で、「自分たちが作りたい動画のイメージに近い実績があるか」をチェックします。スタイリッシュなブランディング動画が得意な会社、コミカルで話題性を狙うのが得意な会社など、それぞれに得意なジャンルがあります。実績を見れば、その会社のクオリティや得意なテイストが一目瞭然です。
Point 2:「コミュニケーション」は円滑に進みそうか
動画制作は、依頼して終わりではありません。企画から納品まで、担当者と何度もやり取りを重ねながら進めていく共同作業です。そのため、担当者とのコミュニケーションがスムーズに取れるかどうかは非常に重要なポイントになります。
問い合わせへのレスポンスの速さや丁寧さ、こちらの意図を正確に汲み取ってくれるか、専門用語を分かりやすく説明してくれるかなど、打ち合わせの段階でしっかりと見極めましょう。ストレスなくやり取りできる相手かどうかは、プロジェクトの成否を左右します。
Point 3:課題解決につながる「提案力」はあるか
優れたパートナーは、こちらの要望をただ形にするだけではありません。こちらの目的や課題を深く理解した上で、「もっとこうすれば効果が高まるのでは?」「こんな表現方法もありますよ」といった、プラスアルファの提案をしてくれます。
自社の要望を伝えた際に、その背景にある課題まで踏み込んでヒアリングし、目的達成のための戦略的なアイデアを出してくれるかどうか。そうした提案力のあるパートナーと組むことで、PR動画の効果を最大化することができるでしょう。
まとめ
今回は、効果的なPR動画の作り方について、企画から活用、外注先の選び方までを網羅的に解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。
- PR動画の成否は、企画段階の「目的」と「ターゲット」設定でほぼ決まる。
- 伝えたいことは「一つ」に絞り込み、ストーリー性で視聴者を「自分ごと化」させることが重要。
- 制作は「企画→撮影→編集→活用」のステップを一つひとつ丁寧に進めることが成功の鍵。
- 自社制作か外注かは、動画の目的、求めるクオリティ、予算、社内リソースを総合的に判断して決める。
PR動画は、もはや一部の大企業だけのものではありません。この記事でご紹介した作り方のステップとコツを実践すれば、あなたの会社やサービスの持つ隠れた魅力を引き出し、多くの人々の心を動かす一本を制作できるはずです。
まずは、あなたの伝えたいメッセージを誰に届けたいのか、じっくり考えるところから始めてみませんか?「trendship」では、これからも動画マーケティングをはじめとする、ビジネスのトレンドを捉えた有益な情報を発信していきます。あなたの挑戦を、私たちは応援しています。