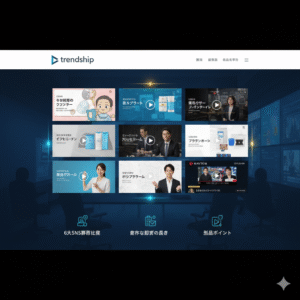「自社の商品をもっと多くの人に知ってほしい」 「商品の魅力を伝えきれず、売上が伸び悩んでいる」 「動画マーケティングに挑戦したいけど、何から始めればいいかわからない」
企業のマーケティング担当者や映像クリエイターの皆さん、このような悩みを抱えていませんか?
情報が溢れる現代において、テキストや静止画だけでユーザーの心を掴むのは至難の業です。そこで注目されているのが、映像と音で直感的に商品の魅力を伝えられる「商品紹介動画」です。
商品紹介動画は、単に製品を説明するだけでなく、ブランドの世界観を伝え、視聴者の共感を生み、購買意欲を大きく高める力を持っています。しかし、ただ動画を作れば良いというわけではありません。目的やターゲットに合わせた戦略的な企画と制作が不可欠です。
この記事では、Webメディア「trendship」の編集部が、数々の成功事例を分析し、視聴者の心を動かし「売れる」商品紹介動画を作るためのノウハウを徹底的に解説します。
かっこいい、面白い、おしゃれな最新の成功事例9選から、企画の立て方、制作のポイント、さらには作った後の活用方法まで、この記事一本で全てがわかります。ぜひ最後までご覧いただき、あなたのビジネスを加速させる一本を制作するためのヒントを見つけてください。
商品紹介動画とは?- 購買意欲を高める最強のマーケティングツール –
商品紹介動画(製品紹介動画)とは、その名の通り、企業が提供する商品や製品の魅力や特徴を、映像と音を用いて紹介する動画コンテンツのことです。
従来のカタログやWebサイトのテキスト・静止画だけでは伝えきれなかった、商品の使用感、動き、質感、利用シーンなどをリアルに表現できるのが最大の強みです。
例えば、アパレル商品であればモデルが着用して動くことで素材の柔らかさやシルエットの美しさが伝わりますし、調理器具であれば実際に料理を作るシーンを見せることで、その手軽さや性能を直感的に理解してもらえます。
このように、商品紹介動画はユーザーに「自分ごと」として商品を体験させ、購買前の不安を解消し、購入への最後の一押しをする強力なマーケティングツールなのです。
ちなみに、有形の商品を紹介するものを「商品紹介動画」、ITシステムやコンサルティングといった無形のサービスを紹介するものを「サービス紹介動画」と呼ぶことが多いですが、基本的な考え方や作り方は共通しています。
なぜ商品紹介動画は重要なのか?制作する3つの目的
では、なぜ今、多くの企業が商品紹介動画の制作に力を入れているのでしょうか。その主な目的は、以下の3つに集約されます。
ブランドイメージと世界観を構築し、競合と差別化する
商品やサービスがコモディティ化(均質化)しやすい現代において、機能や価格だけで競合と差別化を図ることは困難です。そこで重要になるのが「ブランドイメージ」や「世界観」です。
商品紹介動画は、映像のトーン、色使い、音楽、ナレーションなどを通じて、ブランドが持つ独自の哲学や価値観を表現するのに最適なツールです。例えば、高級感を打ち出したいなら重厚感のあるBGMとスローモーションを多用した映像、オーガニックなイメージを伝えたいなら自然光を活かした温かみのある映像、といった演出が可能です。
単なる商品説明に留まらず、ブランドの物語を語ることで視聴者の共感を呼び、価格競争から脱却して「このブランドだから買いたい」というファンを育てることができます。
SNSやWeb広告でのエンゲージメントを高め、認知を拡大する
YouTubeやInstagram、TikTokといったSNSのタイムライン上では、ユーザーは瞬時にコンテンツをスクロールしていきます。その中で足を止めてもらうためには、視覚的にインパクトのある動画が非常に効果的です。
面白さや意外性のある動画は「いいね」や「シェア」をされやすく、爆発的な拡散(バイラル)を生む可能性があります。これにより、広告費をかけずとも多くの潜在顧客にリーチし、商品の認知度を飛躍的に高めることが期待できます。
また、Web広告においても、動画広告は静止画広告に比べてクリック率やコンバージョン率が高い傾向にあります。短時間で多くの情報を伝えられる動画は、ユーザーの興味関心を引きつけ、次のアクションへと繋げやすいのです。
営業・販促活動を効率化し、成約率を向上させる
商品紹介動画は、オンラインだけでなく、オフラインの場でも大きな力を発揮します。
例えば、営業担当者が商談の際に動画を見せることで、口頭での説明だけでは伝わりにくい製品の複雑な仕組みや導入後のメリットを、誰でも分かりやすく均一な品質で伝えることができます。これにより、顧客の理解度が深まり、商談の説得力が増して成約率の向上に繋がります。
また、展示会のブースで動画を流せば、来場者の目を引いてブースへの集客効果を高めたり、スタッフが説明する手間を省いたりと、販促活動の効率化にも貢献します。
効果を最大化する商品紹介動画の作り方|5つのステップ
魅力的な事例を見て、実際に動画を作ってみたくなった方も多いのではないでしょうか。ここでは、成果に繋がる商品紹介動画を制作するための基本的な流れを5つのステップで解説します。
Step1: 目的とターゲットを明確にする(Why & Who)
まず最初に、「なぜ動画を作るのか(目的)」と「誰に見てほしいのか(ターゲット)」を徹底的に明確にします。
- 目的の例:「新商品の認知度を上げたい」「ECサイトのコンバージョン率を5%向上させたい」「営業時の商談成約率を高めたい」
- ターゲットの例:「アウトドア好きの30代男性」「子育てに忙しい20代〜40代の女性」「企業のIT導入担当者」
ここが曖昧なまま進むと、誰の心にも響かない、効果の薄い動画になってしまいます。目的とターゲットが、この後のすべての判断基準となります。
Step2: コンセプトと動画構成(シナリオ)を設計する(What & How)
次に、ターゲットに「何を(What)」伝え、「どのように(How)」伝えるかを考えます。
- 何を(What):商品の最も伝えたい魅力、ターゲットが抱える課題を解決できるベネフィット(便益)は何か?メッセージを一つに絞り込みます。
- どのように(How):ターゲットにメッセージを最も効果的に伝えるためのストーリー(シナリオ)を設計します。課題提起→解決策の提示→具体的なメリット→行動喚起(CTA)といった、フレームワークを活用するのも有効です。
Step3: 表現方法(実写・アニメ・CG)を選定する
シナリオが決まったら、それをどのような映像で表現するかを決定します。主な表現方法には以下の3つがあります。
- 実写:実際の人物や商品を撮影。リアルな使用感や信頼性を伝えたい場合に最適。
- アニメーション:イラストや図を動かして表現。複雑な仕組みや目に見えない概念を分かりやすく伝えたい場合に有効。
- 3DCG:三次元のコンピューターグラフィックス。製品の内部構造を見せたり、実写では不可能なダイナミックな映像を作りたい場合に適しています。
商品やメッセージ、予算に合わせて最適な表現方法を選びましょう。
Step4: 撮影・素材準備・編集を行う
企画が固まったら、いよいよ制作フェーズです。
- 実写の場合:撮影場所の確保、出演者のキャスティング、撮影クルーの手配などを行います。
- アニメーション・CGの場合:イラストレーターやCGデザイナーが素材を制作します。
- 共通:ナレーションの収録、BGMや効果音の選定もこの段階で行います。
全ての素材が揃ったら、編集ソフトを使って映像を繋ぎ合わせ、テロップ(字幕)やエフェクトを加えて動画を完成させます。
Step5: 公開後の分析と改善(Check & Action)
動画は公開して終わりではありません。YouTubeアナリティクスやGoogleアナリティクスなどのツールを使い、再生回数、視聴維持率、クリック率といったデータを分析します。
「どこで視聴者が離脱しているのか」「どの流入経路からの反応が良いのか」などを分析し、サムネイルやタイトルを改善したり、次回の動画制作に活かしたりと、PDCAサイクルを回していくことが成功への鍵となります。
失敗しないための制作ポイント4選
制作フローと合わせて、動画の効果を大きく左右する重要なポイントを4つご紹介します。
冒頭の3秒で心を掴む「フック」を用意する
多くの視聴者は、動画の冒頭数秒で「続きを見るか」を判断します。そのため、最初の3秒で「お、これは面白そうだ」「自分に関係がありそうだ」と思わせる「フック(引っかかり)」が非常に重要です。
インパクトのある映像、意外な質問の投げかけ、ターゲットが共感する悩みの提示など、視聴者の注意を引きつける工夫を凝らしましょう。
情報を詰め込みすぎず、メッセージは1つに絞る
商品の魅力を伝えたいあまり、あれもこれもと情報を詰め込みすぎてしまうのは逆効果です。情報過多な動画は視聴者の集中力を削ぎ、結局何も印象に残りません。
動画制作の目的(Step1)に立ち返り、「この動画で最も伝えたいメッセージは何か」を一つに絞り込みましょう。そして、すべての構成要素をその一つのメッセージを伝えるために最適化することが大切です。
顧客目線で「ベネフィット」を語る
制作者が陥りがちなのが、商品の「機能(Feature)」ばかりを説明してしまうことです。例えば、「この掃除機は毎分10万回転のモーターを搭載しています」と言われても、多くのユーザーはピンと来ません。
重要なのは、その機能が顧客にどのような「便益(Benefit)」をもたらすかを伝えることです。「だから、髪の毛やペットの毛も一瞬で吸い取り、掃除の時間が半分になります」のように、顧客の生活がどう良くなるのかを具体的に語りましょう。
配信媒体に合わせた最適なフォーマットを選ぶ
動画を配信する媒体によって、最適な動画の長さや画面サイズは異なります。
- YouTube:比較的長めの尺で、詳細な情報まで伝えやすい。横型(16:9)が基本。
- Instagram(リール)、TikTok:短尺(15秒〜90秒程度)でテンポの良い動画が好まれる。縦型(9:16)が必須。
- Webサイト:商品ページのメインビジュアルとして使うなら30秒〜1分程度のイメージ動画、使い方を説明するならもう少し長めの動画など、用途によって使い分ける。
事前にどの媒体でメインに活用するかを決め、そのフォーマットに最適化して制作することで、動画の効果を最大限に引き出すことができます。
商品紹介動画の多様な活用シーン
制作した商品紹介動画は、一度作れば様々な場面で活用できる、非常にコストパフォーマンスの高い資産となります。
- Webサイト・ECサイト:トップページや商品詳細ページに埋め込むことで、訪問者の滞在時間を延ばし、商品の理解度を深め、購入率(CVR)の向上に繋げます。
- YouTube・SNS:公式チャンネルでの発信や動画広告として活用し、新規顧客へのリーチと認知拡大、既存顧客とのエンゲージメント強化を図ります。
- 展示会・イベント:ブースのモニターで繰り返し再生することで、集客効果を高め、プレゼンテーションツールとして活用します。
- 営業ツール:タブレットなどに入れて持ち歩き、商談の場で顧客に見せることで、提案の説得力を高め、属人化しがちな営業トークの平準化にも役立ちます。
このように、オンライン・オフラインを問わず、顧客とのあらゆる接点で商品紹介動画は活躍します。
まとめ
今回は、売れる商品紹介動画の成功事例から、具体的な作り方のステップ、そして効果を最大化するためのポイントまで、網羅的に解説しました。
- 商品紹介動画は、商品の魅力を直感的に伝え、購買意欲を高める強力なツールである。
- 目的は「ブランディング」「認知拡大」「販促効率化」など多岐にわたる。
- 成功の鍵は、明確な目的・ターゲット設定と、顧客目線でのベネフィット訴求にある。
- 制作は「目的設定→企画→表現選定→制作→分析改善」の5ステップで進める。
- 一度制作すれば、Web、SNS、営業現場など様々なシーンで活用できる。
商品紹介動画は、もはや一部の大企業だけのものではありません。戦略的に活用すれば、企業の規模に関わらず、ビジネスを大きく成長させる起爆剤となり得ます。
この記事を参考に、まずはあなたの会社の商品で「どんな動画が作れそうか」を考えてみることから始めてみてはいかがでしょうか。もし、動画制作の企画や具体的な進め方でお困りのことがあれば、私たちのような専門家にご相談いただくのも一つの有効な手段です。
あなたの商品の魅力が詰まった一本が、未来の顧客の心を動かすことを願っています。